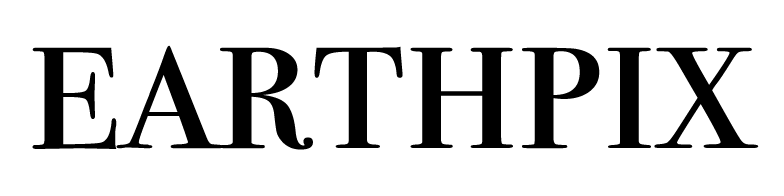海に浮かぶ赤い鳥居が美しい厳島神社の魅力
宮島口からフェリーに乗ると、海から神社に参拝するように大鳥居が見えます。水の中に浮いたような壮麗な建物の数々。平家納経で知られる安芸の宮島です。
平清盛が深く崇敬し、現在の海に浮かんだ寝殿造の華麗な社殿が建てられましたが、その後も毛利元就、江戸時代には広島の浅野家が庇護してきました。
島全体が神域とされた環境は建物と一体化し、平安時代の雰囲気を今に伝え、日本人の美意識の基準の1つとなっていることが世界遺産に選ばれた理由です。
海に浮かんでるみたいな大鳥居
本社火焼前(ひたさき)から沖合160mほどの海面にそびえます。高さ16mの朱塗りの大鳥居は重さ60tほどありますが、根元を海中に埋めるのではなく鳥居の重みだけで立っています。
潮が満ちて海に浮かんでいるように見える大鳥居も美しいですが、新月や満月の時は潮の干満差が大きく、干潮の時は鳥居の根元まで歩いて行くことができます。
寝殿造りの本殿は平安時代のまま
海の守り神、宗像三女神を祀る本殿は檜皮葺の屋根の寝殿造りの様式です。千木や鰹木を持たない、神社らしからぬ華麗な建物です。
本殿の前に広がる床は平舞台といい、いわば庭にあたる部分ですが、高潮でも浮き上がらないように、また雨の水はけも考えて木材にわざと隙間を作ってあります。ここを支える柱は赤間石でできていて毛利元就の寄進だそうです。
能舞台も浮かんでいます
海に浮かんでいる能舞台は日本で唯一のものです。海上にあるので足拍子の響きを良くするために舞台の床は1枚の板のようになっています。春の桃花祭の神能はここでおこなわれます。
社殿から社殿は廻廊で結ばれています
本殿や能舞台などの社殿は廻廊で結ばれています。幅4mの廻廊の床板には、やはり目透かしと呼ばれる隙間が作られています。現在、廻廊の床板は本来のものの上に参拝者が土足で歩けるように覆い板が敷かれた二重構造になっています。
勅使橋とも呼ばれます
美しい反橋ですが、かつては重要な祭事の折などに天皇の使いである勅使がここを渡って本社に入ったので勅使橋とも呼ばれました。擬宝珠の刻銘を見ると毛利元就・隆元父子が再建した事がわかります。
和風、唐様とりまぜた五重塔
1407年に建立されたと伝えられる五重塔は檜皮葺の屋根は和風ですが、屋根の反りが大きいのは唐様を取り入れています。内部は唐様の造りになっています。
弥山に登ってみましょう
厳島神社の背後には原始林が広がっています。古くから神域として神職でも祭事以外は上陸できなかった宮島ならではです。健脚なら歩いても、簡単に登るならロープウェーもあります。
山麓の紅葉谷公園はその名のとおり紅葉の名所ですし、神仏習合の時代を経たたくさんの寺院も点在しています。頂上からは美しい瀬戸内の海や四国まで見ることができます。
まとめ


Photo by Shutterstock
平家にあらずんば人にあらずと言われた平清盛の栄華の跡がしのばれます。
潮が満ちている時と引いている時では景色が全く違って見えますので時間に余裕を持って訪れましょう。
❐【世界遺産登録へ!】明治日本の産業革命遺産 近代化を支えた長崎の歴史
❐【世界遺産 】希少種の宝庫小笠原諸島のボニンブルーがマジで綺麗
❐世界遺産「白神山地」に広がる太古の森を探検したくなる魅力まとめ